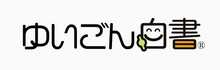- ホーム
- 今日のマリリンのつぶやき
今日のマリリンのつぶやき
2/7(土)東品川にて「新しい終活ツール✏️
「ゆいごん白書®︎」作成講座を開催決定❣️
2026/01/19
Air Business Departure略して「エアビジ」
女性のためのコラボワーキングサロンにて2/7・8とマルシェが開催され、
その1コマとして2/7(土)15時〜17時に「ゆいごん白書®︎」の作成講座を開催しまーす✨
【会場】Air Business Departure略して「エアビジ」
東京都品川区東品川3丁目25-17 3階
🚃りんかい線「品川シーサイド駅」より徒歩約6分
🚃京急本線「青物横丁」より徒歩約8分
老少不定(ろうしょうふじょう)
2026/01/17浄焚(じょうぼん)
2026/01/161/27 「ゆいごん白書®︎」作成講座
2026/01/13丙午の年(ひのえうまのとし)
2026/01/02十干(じっかん)の丙(ひのえ)と十二支の午(うま)が組み合わさった年で60年に一度巡ってきます。
2026年が丙午にあたり、火の性質が強く情熱的でパワフルな年とされる一方で、「丙午生まれの女性は
気が強く、夫の命を縮める」といった迷信(特に「八百屋お七」が丙午生まれとされたことから)で知られ、
過去には出生数の減少(産み控え)を 引き起こしたこともあったようです。
悔過(けか)
2025/12/30南都六宗(なんとろくしゅう)
2025/12/29仏教において、奈良時代に平城京(奈良)で栄えた6つの宗派。三論宗(さんろんしゅう)
成実宗(じょうじつしゅう)・法相宗(ほっそうしゅう)・倶舎宗(くしゃしゅう)・華厳宗(けごんしゅう)
律宗(りっしゅう)の総称で、奈良仏教とも呼ばれており、国家仏教として公認された宗派だそうです。
注連縄を飾る日(しめなわをかざるひ)
2025/12/28一般的に12/26〜28の間に飾り、本日28日がいいそうです。または30日でもよいとか。
本日12/28がいい理由として「8」は末広がりの意味があり、繁栄や幸運を象徴するからだそうです。
逆に避けたい日として、12/29は二重の苦と読めたり、12/31は「一夜飾り」と言い年神様に対して
失礼にあたるとされているようです。一夜飾りで年神様を迎えるのは失礼という意味だそうですよ。
久米島での宗派
2025/12/22🌹葬儀費用の見積もり同行モニター1名様 募集します
2025/12/21*直接、お目にかかった事のある方限定🙏
🌹葬儀費用の見積もり同行モニター募集🌹
通常20,000円の所、
モニター1名様を募集します😊
2社の葬儀社に行き、
実際に見積もりを取ってみませんか?
*葬儀社はご自身で2社お決めください。
*一日で終わるように段取りつる予定です。
終了後、簡単なアンケートにご協力を
お願いいたします🙏
詳細はコチラ👇
*交通費実費をお支払い願います🙏
関西でしたら、
JR京都線「千里丘」駅
or 阪急京都線「摂津市「駅からの金額。
東京でしたら、
東京メトロ千代田線「千駄木」駅からの金額。
⚠️東京の場合は、私が東京に行く日となるので、
こちらの日程に合わせていただくことになります🙏
*試してみたい方、
ご連絡くださいませ❣️
こんな機会に是非!
お見積もりを取ってみてくださーい😊人生会議(じんせいかいぎ)
2025/12/17-
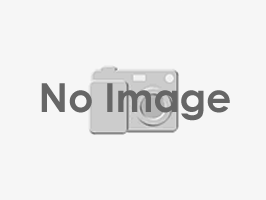 1/27 「ゆいごん白書®︎」作成講座
ありがたいことに、この日は満席🈵になりました❣️もしご興味おありの方、受けてみたいなと思われた方は、是非👇をご
1/27 「ゆいごん白書®︎」作成講座
ありがたいことに、この日は満席🈵になりました❣️もしご興味おありの方、受けてみたいなと思われた方は、是非👇をご
-
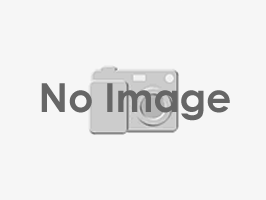 玉串奉奠(たまぐしほうてん)
神道において、榊の枝に紙垂をつけた「玉串」を神前に捧げて祈念する作法のこと。仏教で言うならば、焼香にあたる大切
玉串奉奠(たまぐしほうてん)
神道において、榊の枝に紙垂をつけた「玉串」を神前に捧げて祈念する作法のこと。仏教で言うならば、焼香にあたる大切
-
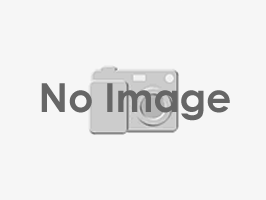 納骨式(のうこつしき)
故人様のお骨を、お墓や納骨堂などへ埋葬する儀式(法要)のことを言います。
納骨式(のうこつしき)
故人様のお骨を、お墓や納骨堂などへ埋葬する儀式(法要)のことを言います。
-
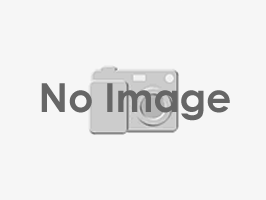 浄焚(じょうぼん)
古くなったり、不要になったお位牌・お札・お守り・人形・写真など、粗末に捨てられないものを、読経などをあげていた
浄焚(じょうぼん)
古くなったり、不要になったお位牌・お札・お守り・人形・写真など、粗末に捨てられないものを、読経などをあげていた
-
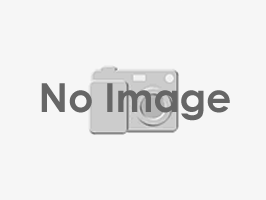 老少不定(ろうしょうふじょう)
人の命は、老いや若さは関係なく定まっていない。という意味で、年老いた人が必ず先に死に、若者は後から死ぬとは限ら
老少不定(ろうしょうふじょう)
人の命は、老いや若さは関係なく定まっていない。という意味で、年老いた人が必ず先に死に、若者は後から死ぬとは限ら